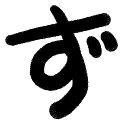2006/01/30
■ ぐるぐる / 雰囲気
爆発の危険性がある雰囲気の話。コメントで書いちゃったけど、補足。
私が最初にこの表記を見たのは、日経エレクトロニクスの記事。 半導体のウェーハーの加工のあたりで、窒素雰囲気とか酸素雰囲気とか出てきて、 言いたいことはわかるけど、なんだこりゃ、って思ったのが最初。
でもまあ、定期購読しているうちに慣れました。世の中そんなもんかも。
爆発絡みだと、先月読んだ実験室の笑える?笑えない!事故実例集あたりを読むといいかも。
■ バス / 時間調整
最近は、ECOバス(那覇バスの新6番線)で帰ることが多い。 今日、バスで興味深いことに気がついた。
通常(というのもなんだが)、沖縄のバスは無人の停留所では止まらない。 俗に「タクシーは手をあげなくても止まるが、バスは手を挙げないと止まらない」と 言われる所以である。
ところが、今日乗ったバスは無人であっても停留所で止まるし、 運転手がちらちらと腕時計を見ている。
どうやら内地ではあたりまえの「時間調整」をしているっぽい。 それも無人のバス停に止まる時間をこまめに調整して、 さりげなく調整しているようだ。 偉い! 偉いぞ那覇バス。
沖縄のバスで何が困るかって、バス停にある時刻表が役に立たないこと。 遅れるだけならまだしも「早く来たりする」ので、いざバス停についても バスが通過したのかしないのかさっぱりわからない。 慣れてくるとバス停に待っている人がいるかどうかで判断したりするけど、 それも確実じゃないし。
少なくともバス停に書かれている時刻よりも早くは通過しないということが わかっていれば、だいぶ楽なんだが。従来の沖縄のバス会社はそれすら できてないわけで...orz...
ということで、次回、那覇バスに乗るときはみんな注意して欲しい。 特に市内線は教育が行き届いているように思う。
2006/01/28
■ OIA勉強会
pekoさんとlouieさんの発表。 面白いけど、もうちょっと喋って欲しかったなあ。 続編に期待。
2006/01/26
■ 明後日はOIA勉強会
第87回 OIA勉強会は明後日開催。今回はWebデザイン系の話題。起ききれるかな...(^^;
2006/01/24
■ ぐるぐる / 偏差値70からの大学受験!? ぼく、偏差値大好き
偏差値70からの大学受験!? ぼく、偏差値大好き。壮絶なドラマ。つい全部読んでしまった。
2006/01/23
■ ネタ / 脳内汚染
ircで教えてもらったネタ。
脳内汚染のレビューが凄いことになってる。まあ、本が本だから仕方ないけど。
2006/01/21
■ DS / どうぶつの森
おいでよどうぶつの森、始めました。
娘のDSを奪って使ってるんだけど、面白いですねえ、これ。 WiFiの使いかたもいい感じだし、やるな任天堂。
2006/01/20
■ サンエー楽天に上場...ではなくて
サンエー、楽天に出店らしい。東証1部にも上がるようだし、元気がありますなあ。
■ ニュース / 米国産の輸入牛肉、危険部位混入の疑い
- 米国産の輸入牛肉、危険部位混入の疑い(朝日新聞)
- 輸入米牛肉:特定危険部位のせき柱混入 中川農相「遺憾」(毎日新聞)
- 米国産牛肉、危険部位混入の疑い 成田で発覚(産経新聞)
さすがだ...ということで、BSEに追記。
追記: 米国産牛肉輸入、再び全面停止へ(TBS)
■ JUNET / 風の谷のナウシカ
ぐるぐるしてたら、 JUNET 87年冗談大賞受賞作品 「風の谷のナウシカ」を発見。なつかしー。読んだ覚えあるぞ。fjかなんかに流れてたんだっけなあ。
2006/01/19
■ PC / Celeron 450MHz * 2 なPC譲ります
私の知人が、Celron 450MHz デュアルなPCを放出したいと申しております。 ご希望の方は、mixiのメッセージかircで御連絡ください。 フルタワーです。440BXチップセット。ディスクは要交換。
これは、大昔に私が譲ったものだったりするのだ...
2006/01/18
■ 本 / 幾何への誘い
幾何への誘い、小平邦彦著、岩波現代文庫—学術7。
私はどうやって数学を学んだのだろうか? と思うことがある。
記憶に残っているのは、 沖縄県立図書館の蔵書の数学書、算数自由自在 、ブルーバックス 各種。小学3年生ぐらいから読んだかなあ。当時の図書カードが残っていれば良かったのだが。
特に、県立図書館で読んだ、ユークリッドの原論を基にした幾何の本が 印象に残っている。ちなみに、近所の那覇市立中央図書館は、一般向けの本しかなくてあまり好きではなかった。
ということで、昔風の本を探しているのだが、これがなかなか見つからない。 ようやく見つけたのが 幾何への誘い。筆者はフィールズ賞受賞数学者。序章にもあるように、旧制中学の平面幾何を元にしていて、面白く読める。やや難易度は高い。実際に紙とペンがないと解けない問題もあるが、頭の体操にはいいかも。最後の方は複素数と平面幾何の関連を解説していて、これも良い。
数学を再勉強したい人にお勧めかなあ。とりあえず娘に読まそう...
そういえば、 物理の散歩道 も再版して欲しいなあ。amazonの中古で買えるけど高すぎ...
■ 本 / 視覚世界の謎に迫る
視覚世界の謎に迫る—脳と視覚の実験心理学、山口真美著、ブルーバックス。
筆者は主に乳児の視覚世界を研究している心理学助教授。この本も、主に乳児や幼児など発達期の児童の視覚世界研究から得られた所見を元に、人間の視覚について説明している。 面白いしお勧め、だけど、タイトルから受けるイメージと違うなあ(^^;
■ 本 / 越境としての古代〈3〉
越境としての古代〈3〉、越境の会編集。
越境としての古代、越境としての古代〈2〉、に続く3冊目。
例によって、 九州王朝説を前提にしている。まあ、それはいいとして、どんどん上に仮説を積み上げていくので、トンデモの領域に入っているかもしれない。
それにしても、古代史を追求していくと、韓国史とか中国史とかアジア史になるってのはなぜだろうか。 桓檀古記 (google:桓檀古記)まで出てくると、かつての鹿島昇 と同じ路線だよなあ。何かがあるのだろうか。
ということで、毎度ながら九州王朝とかに違和感のない人にお勧め。
■ 本 / 図解 クトゥルフ神話 F‐Files
図解クトゥルフ神話F‐Files、森瀬繚著、新紀元社。
書名の通りの本。入門にはいいかな。イアイアハスター
■ 本 / 円周率πの不思議
円周率πの不思議、堀場芳数著、ブルーバックス。
駄本。ブルーバックスも堕ちたものだ...と、何度思っただろうか。 とりあえず、この著者の本は買わないリスト行き...
2006/01/05
■ ぐるぐる / 鷲巣麻雀牌
知ったかぶり週報の2006/01/04の記事から、【ファンキー通信】自分も相手もまる見え!? 不思議な麻雀牌。
いいな、これ。ちょっと欲しいかも。http://www.1kawaya.com/ で 38000円かあ...
2006/01/04
■ 某店のPOP
POPといっても Post Office Protocol ではない、つーか。
某店に行ったら、こんなPOPが... をー、やるときはやるじゃん!、5割引とは太っ腹! と、期待して近づいたら....
これはちょっとなー
追記: 最近行ったら、このPOPは無くなってた。 いまは、FastTrack のRAID用IDEカードが1000円で売られているけど、微妙。
2006/01/01
■ 謹賀新年
今年もよろしくお願いいたします。
■ 雑誌 / ニュートン 2006年2月号
ニュートン2006年2月号、ニュートンプレス。(ニュートン定期購読)。
特集は『「性」を決めるカラクリ XY染色体』。女性天皇についての議論が されているところへタイムリーというべきか、商売上手と言うべきか。 内容は、科学的な部分のみに的を絞っていて、素直に読めるし、よくまとまっている。
他に興味を引いたのは、「3億年を生きぬいた三葉虫の世界」。 さまざまな種類の三葉虫の化石をカラー写真で紹介している。写真を見るだけでも 面白い。もうちょっと文章が多くてもいいなあ。
■ 雑誌 / 言語 2005年12月号
月刊言語2005年12月号(大修館書店)
特集は「日本人と日本語」。そのなかでも「最新のデータに見る日本人の言語行動-年賀状に関する調査をもとに」が面白い。
「差出人の年齢と年賀状の縦書き/横書きの比率」や、賀詞の言語、電子メールの利用割合などから分析を行っている。傾向のグラフを見ているだけでもいろいろなことを想像してしまう。次回の調査時はmixiで年賀状を出すの比率が結構高くなるんじゃないか、あるいは、今では想像もできない手段が使われているのだろうか。
連載だった「手話の言語学」は今月で終了。いい連載だったので本になるといいのだが。
■ 本 / アマ4段を越える コンピュータ将棋の進歩
アマ4段を超える—コンピュータ将棋の進歩〈4〉、松原仁著、共立出版。
コンピュータ将棋の現状について時々でているシリーズの4冊目。さまざまな将棋プログラムのアルゴリズム紹介が主。まだまだ新しい探索手法が提案され、棋力が強化されているのが頼もしい。もはや、私はコンピュータ将棋には勝てなくなって久しいが、読んでいて面白い。コンピュータ麻雀の本も出るといいんだけどなあ。 お勧め。
■ 本 / 実験でわかる物理のキホン!
実験でわかる物理のキホン!、潮秀樹著、小池清之著、大野秀樹著、松本浩之監修、秀和システム。
出版社の秀和システムといえば、昔はPC9801の解析本でお世話になったのだが 昨今は科学系の本も出しているようだ。これは、入門科学シリーズの第一弾。
内容は、身近な道具を使った物理実験で、まあよくある入門本。 写真とイラストがわかりやすいのと、物理的な説明がきちんとできてるのがいい。 お勧め。
■ 本 / 畑村式「わかる」技術
畑村式「わかる」技術、畑村洋太郎著、講談社現代新書。
「わかる」ようになるための本。書いていることはまったくその通りなんだけど、 これを読むと「わからない人がわかるようになる」とは思えない。「わかってる」側から読むと「そうなんだよね」と同意する部分は多いのだが。
むしろ、わからない人に教えるための入門書として読むのが適切じゃないだろうか。
■ 本 / 生きづらい<私>たち
生きづらい<私>たち-心に穴があいている、香山リカ著、講談社現代新書。
満たされない・傷つきやすい・心に穴があいている・鬱、などの現代的な症例について香山リカが解説した本。秀逸なのは、169頁の図。さまざまな症状(神経症・ひきこもり・自傷行為・摂食障害・解離性障害・PTSD・境界性人格障害)のベースにうつ気分があって、むしろさまざまな症状は派生した枝葉の問題ではないかと指摘している。この指摘は重要だと思う。お勧め。
■ 本 / 日本語の謎を探る—外国人教育の視点から
日本語の謎を探る—外国人教育の視点から、森本順子著、ちくま新書。
日本語文法の本は、外国人に日本語を教えている人が書いた本の方が面白いし、役に立つと思っている。この本も留学生に日本語を教えている筆者の目からみた日本語論。お勧め。
しかし、この手の本を読めば読むほど、学校文法の方が謎に思えてくる。 なんであんなの教えてるんだろ。三上章の象は鼻が長いでも読ませた方がいいように思う。
■ 本 / 脱オタクファッションガイド
脱オタクファッションガイド、久世原案、トレンド・プロ制作、晴瀬ひろき作画、オーム社。
かつてのオーム社を知る者としては、このような本まで出すようなったかと、感慨深いものがある。それはさておき、本書は同名のオタク向けのファッション入門サイトの内容を書籍化したものである。元々のサイトの内容に加えて、各章には短い漫画で導入をしているし、かなりわかりやすくなっていると思う。いい本だけど、誰にお勧めすればいいのだろうか(^^; 漫画のオチは想像通りで、なんというか。
188頁の指摘「一般に女性ファッション誌は完璧なマニュアル本で…極めて実用的な内容になっています。しかし男性史の場合…そのほとんどが…カタログ式であり、ちょっと目を通しただけでは分かりにくい内容です」ってのはその通りだと思う。こういう指摘はいままで無かったのだろうか。