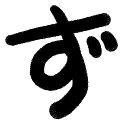2005/11/30
■ ぐるぐる
日本軍事情報センターの11月18日の記事。なるほど、そう読むのか。深い。
「それにしてもキャンプ・シュワブの新飛行場建設案の延長線上にゴルフ場があることや、隣接する場所に辺野古ダムがあるのに驚いた。原案だった辺野古沖合埋め立て基地などとは、比較できないほど沿岸案は軍事的な条件を満たしている。軍事ではまず地図を見ることから解析が始まる」
2005/11/24
■ 那覇バスのWeb
那覇バスのページを発見。結構いけてると思う。 那覇バス株式会社ブログで、運航状況などを報告してるのもいい。
2005/11/23
■ マシン買い替え
マシン壊れたので仕方なく代替機を買いに行く。 どうせだからAthlon64 X2にしてみる。 メモリ1GB。ディスクやAGPカードは壊れたマシンからはぎとる。 MTVX2004を安売りしてたので、それも買う。
OSはディスクに入っているものをそのまま使った。 デバイスマネージャーで、コンピュータの設定を「ACPIユニプロセッサPC」から 「ACPIマルチプロセッサPC」に変更するだけでマルチプロセッサとして認識している感じ。
2005/11/22
■ またマシン壊れたっぽい
この時期(夏が終わって寒くなりだしたころ)になるとマシン壊れる。 なんでだ。
追記: その後の調査の結果、以下のことがわかった。
- しばらく放置しておけば、ちゃんと起動すること *も* ある。
- でも、一度起動してから電源を切ると、再起動しなくなることがある。
- 仮に起動できても、なぜかイーサネットが使えない。
2005/11/20
■ TV / 難問解決ご近所の底力
取り溜めたTV番組を整理しながら試聴。1か月近く前の10月27日放送の「これでいいのか!子どもの食卓」が凄い。
内容は「偏食する子供、ちゃんと料理が作れない親を地域が救う」というよくある筋書き。まあ、それはそれでいいんだが、ここで実例として出てくる子供の食事が凄い。「どんぶりご飯に駄菓子を乗せたり」という駄菓子丼とか、一日の食事のうち9割が菓子パン(残りはゼリー)とか。もしかして、これでも良い方だったりしてなあ。
■ PC / ビデオ編集
取り溜めたTV番組は、本編だけを切り出してタイトルをファイル名としてつけて保存している。時々、視聴できるのに編集できない謎のファイルが録画されていることがある。今回も大はまり。VideoStudio6で逃げられたけど、なんでこうなるんだろ。
TV録画と編集に少し追記。
追記: あとで確認したら、編集したファイルの映像と音声の同期が合っていない。どうも、元々のデータが妙な具合になっているようだ。音声と映像を分離して、必要な部分の切り出しはできたのだが、再結合ができない....困った。
2005/11/14
■ 本 / 茶色の朝
茶色の朝、フランク・パヴロフ、ヴィンセント・ギャロ、藤本一勇、高橋哲哉。 大月書店。
kojさんの日記で紹介されていた本。全体主義の恐怖、あの時代の恐さを描いた本なんだけど。うーん。入門書なのでこんなもんかという感じが半分。期待しすぎたかな。イラストが抽象的でよーわからんのは私が左脳人間だからか。娘に読ませよう...
■ 本 / 日本語文法の謎を解く—「ある」日本語と「する」英語
日本語文法の謎を解く—「ある」日本語と「する」英語、金谷武洋著、筑摩書房。
著者はカナダで日本語を教える教師。「外国人に日本語を教える」立場で 日本語を見たときにわかったことをきちんと書いてある。 英語を学ぶ上でも日本語を学ぶ上でも参考になる本だ。お勧め。
ただし、日本語についてはいわゆる学校文法ではなく三上文法を継承しているので、 気になる人は気になるかも。私は三上文法の方が正しいと思うので気にならないが。
同じ著者の 日本語に主語はいらない—百年の誤謬を正す、や、もはや古典ですらある三上章の 象は鼻が長い—日本文法入門を併読するとなお良いと思う。
■ 本 / 闘えない軍隊 肥大化する自衛隊の苦悶
闘えない軍隊 肥大化する自衛隊の苦悶、半田滋著、講談社。
自衛隊のイラク派遣をメインに、政治と自衛隊とメディアの関係を明るみにする本。 シビリアン・コントロールの名の元に横行する責任逃れが、かえって、自衛隊も 国も窮地に追いやっているのは、かつての日本軍と同じ構造なのだろうか。 責任を現場の裁量に押し付ける構造は、日本のあちこちで見られる。 自衛隊や国防だけでなく、組織論としても読める。お勧め。
失敗の本質—日本軍の組織論的研究と併読するといいと思う。
■ 本 / 知っておきたい漢字の知識
知っておきたい漢字の知識、阿辻哲次著、柳原出版。
著者の阿辻哲次 氏は、漢字・漢字文化・文字コードの大家。その大家による漢字学入門。漢字について一通り標準的な知識を得るには良い。 漢字入門にはお勧め。娘に読ませよう...
■ 本 / モノの原価がまるごとわかる!—得するウラ情報の最新版!
モノの原価がまるごとわかる!—得するウラ情報の最新版!、マル秘情報取材班編集、青春出版社。
最近、この手の原価本は何冊も出ていて、私もいくつか持っているのだけど、 ふと買ってしまった。まあまあ。原価本の水準には達してるとは思う。
2005/11/13
■ 書店のレシート
ふと気がついたのだけど。
書店によって、くれるレシートの情報量が違う。 下記は琉大生協とパレット久茂地7FのLIBROのレシート。 琉大生協は書名まで入っていて、LIBROは書名だけ。
どちらが親切なのだろうか。もしかしたら、LIBROは「人に言えないような本」を買う人のことを考えて、あえてそっけない記載にしているのだろうか。謎だ。
2005/11/07
■ 妻PC作成
2001/09/01に購入した妻PCがお亡くなりに。 電源を入れてもディスプレイに何もうつらない。 電源ユニットを置き換えてもダメなので、マザーボード死亡っぽい。
仕方がないので(喜んで)PCを買いにいく。 PC工房、GoodWillとも安いのはCeleronDだが、それでは納得できないことにして、 だとthlon64の安いパーツで1台組む。結構な値段になる。 OSのインストールまでは楽勝。速い速い。
で、ここから苦労が始まる。
妻はデジタル家計簿というソフトで家計簿を付けているのだが、それのデータが古いPCのディスクからもってこれない。ディスクも一部変なのか、そのディスクを他のマシンにつけてもOSが起動しない(途中でブルースクリーン)。データはmdbなのだが、管理データがもってこれない...
24時間悩んだ末に以下の方法で解決。まず、家計簿ソフト(Program Files以下)とデータをコピーしておく。次に、そこに上書きインストールで家計簿ソフトを入れる。これだけ。あの苦労はなんだったんだ...
2005/11/01
■ 10月に読んだ本
もう11月だよ...
■ 本 / ごまかし勉強 上・下
ごまかし勉強(上)学力低下を助長するシステム 、ごまかし勉強(下)ほんものの学力を求めて、 藤澤伸介著、新曜社。
目から鱗。今まで読んだ教育書の中でもっとも参考になった。 お子様をお持ちの方、一読をお勧めします。
この本で言う「ごまかし勉強」、私なりの理解では「全ての場面で一夜漬けしかしない勉強」を指します。最低限の学習範囲(間に合わない・難しいところは捨てる)、すぐに忘れてもいいので単純丸暗記、一見成績は悪くないけどだんだん学力が低下する。
しかも、学校の先生や塾、参考書業界までがごまかし勉強を推奨。 ごまかし勉強の再生産すら行われている始末。
思い当たるフシ満載。ということで、子どもの勉強を見直し。 なんというか、問題だとわかってしまえば直せるかもしれないという気になります。 工数かかるけど...
ドラゴン桜あたりと併用するといいかもしれません。
■ コミック / 大奥(1)
大奥(1)、よしながふみ著、ジェッツコミックス。
パラレルワールド時代劇SF。よしながふみ 偉い! 面白いっす。
■ 本 / わかったつもり
わかったつもり 読解力がつかない本当の原因、西林克彦著、光文社新書。
本を通りいっぺんに読んだだけでは「いかにわかったつもりになっているか」 ということを実例を交えて教えてくれる本。この本もいいですね。 子どもに読ませてもいいかも。
■ 本 / 新編 教えるということ
新編 教えるということ、大村はま著、ちくま学芸文庫。
最近お気に入りの大村はま先生の本。教えるということはどういうことなのか、 どれだけ真摯にならないといけないことなのか。いまの教員で大村先生の期待に 応えられる人はどれだけいるのだろうか。
一般の方は教師についての見かたを学ぶために、教師の方は自戒のために 読んで欲しい本。お勧め。
■ 本 / 素数ゼミの謎
素数ゼミの謎、吉村仁著、文芸春秋。
北アメリカ大陸にいる、13年ないし17年周期で地上に出てくる蝉についての本。 絵も多いし、科学の入門にいいと思う。小学生高学年ぐらいが対象かなあ。
■ 本 / 下流社会 新たな階層集団の出現
下流社会 新たな階層集団の出現、三浦展著、光文社。
小泉改悪政権の元で貧富の差がさらに開きつつある日本。 人々を上・中・下の3つに分類し、それぞれの階層の行動パターンを 赤裸々に書いた本。男性は年収300万未満では結婚できないとか、 自分らしさを求めるのは下流だとか。辛い指摘が多いが、お勧め。
■ 本 / 議論のウソ
議論のウソ、小笠原喜康著、講談社現代新書。
前半はよくある騙されない方法。これはこれで参考になるのだが、主旨は 最後の1章。安易に真偽を決める・ウソを見抜いたつもりになることを戒めている。 これもお勧め。
■ 本 / 計算力を強くする
計算力を強くする、鍵本聡著、ブルーバックス。
子どもに読ませるための本。 よくある計算ノウハウ本。昔なら基礎的なことだったんだけど、今では 教えないといけない… 私としては、こんなもんかなという感じ。
■ 本 / 中国文明の歴史
中国文明の歴史、岡田英弘著、講談社現代新書。
神代から夏・殷を経て清に至るまでの「中国」志。 そもそも「中国」とは何なのかという問いに答える本。 興味深く読めた。一部同意できない(というか、真偽不明)の説はあるが 「中国」の理解を深める本だと思う。お勧め。
しかし、この本の「中国語」の成立に関わる話は本当なのだろうか。 この辺を書いている本を読みたいなあ。
■ 本 / 人口から読む日本の歴史
人口から読む日本の歴史、鬼頭宏著、講談社学術文庫(1430)。
縄文時代から現代に至るまでの日本の人口の推移を、丹念に調査し、 解説している本。今からではつい忘れがちになる、幼児死亡率の高さが 社会に与える影響や、都市における高い死亡率など、再考させてくれる。
人口減少社会を語る前に読む本だと思う。お勧め。
■ 本 / 歴史人口学で見た日本
歴史人口学で見た日本、速水融著、文春新書。
さて、昔の人口をどうやって推測するのか? 宗門改帳やその他の資料を元に、どのように過去の人口動態を分析したのかを 解説する本。前節で紹介した「人口から読む日本の歴史」と合わせて読むと いいと思います。お勧め。
■ 本 / 日本の歴史をよみなおす
日本の歴史をよみなおす、網野善彦著、ちくまプリマーブックス。
日本の識字、金融、差別など、網野流の歴史入門書。 まあまあかな。
いまでは文庫が出ているようなので、そちらを買うのがお得かも。 日本の歴史をよみなおす(全)。
■ 本 / 分解!
「分解!」 日用品・自転車を分解してみると! 分解!-壊せば道理が見えてくる-、堀内篤著、技術評論社。「分解!」 家電品を分解してみると! 分解!-壊せば道理が見えてくる-、藤瀧和弘著、技術評論社。
分解…なんと心躍る言葉だろう。時計、ラジオ、その他を分解して元に戻せなくなった経験のある人にお勧め。さまざまな製品を分解してみせてくれる楽しい本。 お勧め。
■ 本 / 老ヴォールの惑星
老ヴォールの惑星、小川一水著、ハヤカワ文庫JA(809)。
ホットジュピターを舞台にした表題作などのSF短編集。 海外のSFと比べると深みが少ないかなあ。お勧め。
■ 本 / パズルでひらめく補助線の幾何学
パズルでひらめく補助線の幾何学、中村義作著、ブルーバックス。
ちょっとひらめきが必要な幾何学の問題が76問。 幾何学に興味がある人にはいいかな。
■ 本 / 倭国神話の謎 - 天津神・国津神の来歴
倭国神話の謎 - 天津神・国津神の来歴、相見英咲著、講談社選書メチエ。
日本書紀や古事記の記述を元に古の倭国を探る本。 筆者の主張には同意できないが、記紀の分析方法は参考になる。面白い。
■ 本 / 人類進化の700万年—書き換えられる「ヒトの起源」
人類進化の700万年—書き換えられる「ヒトの起源」、三井誠著、講談社現代新書。
過去700万年の人類進化史について。筆者の説は通説(アフリカ一元説)とは異なるのだが、そこを何度も説明するのでちょっと辛い。日経サイエンスの別冊あたりを読んだ方がいいと思う。
■ 本 / 日本を滅ぼす経済学の錯覚
日本を滅ぼす経済学の錯覚、堂免信義著、光文社。
筆者は元はコンピュータ関係のエンジニア。退職後 経済学を自学し、 この本を著した。筆者のさまざまな疑問を元に日本経済学への処方を書く。
と、書くといい本に聞こえないこともないけど、はっきり言ってトンデモ本。 筆者は現在の経済学を酷評するけど、酷評されてるのが竹中平蔵… お願いだからちゃんとした経済学の本を読んでくれ。 (いや、文献リストにはクルーグマンも載ってるけど、ちゃんと読んでなさげ)
この本買うぐらいなら、クルーグマン買ってください。