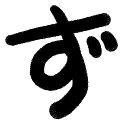2005/02/28
■ ぐるぐる
ヒアテキストではなくてヒアドキュメントだと思います。
■ 南セントレア市
住民投票で合併破綻になった模様。まあそうだよなあ。あまりにも恥ずかしい。 どうせなら、命名権を売って市の財源にすればいいのに。すげー儲かったかも。
南セントレア市FLASHつーのもあるのか。すごいな。
■ Opera8β2
Opera8β2が出てるようだ。Operaが次期ブラウザのベータ2公開、フィッシング対策に大幅な改良を参照のこと(余談だが「フィッシング対策を大幅に改良」のほうが日本語として素直じゃないかなあ)。
βいくつなのかは Help->About OperaのBuild を見ないと判別できない。 β1がBuild 7401、β2が7483である。
2005/02/27
■ Opera / NTT西日本
NTT西日本の名前をかたった強引な商法に注意のページをOpera8βで見ると、うまく見えない。隠し文字っぽくなる。なんでだろ。
追記: Operaの問題じゃないっぽい。特定のマシンで発生している。何が悪いんだろ。
■ 土星の写真
土星のポートレートと自転周期の話からThe Greatest Saturn Portrait ...Yetへ。土星の写真が美しい。自宅のプリンタはヘッドがへばってきたのか、綺麗に印刷できない。こういうのをでかく(A0とかA1とか)印刷できるサービスで、適当なのってどこかにないかなあ。
■ 本 / バリバリのハト派
バリバリのハト派—女子供カルチャー反戦論、荷宮和子著、晶文社。
荷宮和子は、以前は「クマの時代—消費社会をさまよう者の「救い」とは」や、「少女マンガの愛のゆくえ」など、消費社会や若者、宝塚をキーワードにした本を出していたのだが、最近は世相を憂いた本を出すようになっている。たとえば、「若者はなぜ怒らなくなったのか」や「声に出して読めないネット掲示板」など。
大塚英志も含めて、従来とは違った層(オタク?)からリベラルな発言が出てくるようになっている。そして、その層の本のほうが従来の左翼の本よりも説得力があったりする。
ということで、この本はお勧め。後半がちょっと宝塚ネタが多すぎるような気もするが許容範囲だろう。
■ 本 / パラサイト社会のゆくえ
パラサイト社会のゆくえ、山田昌弘著、ちくま新書。
著者の山田昌弘は、1999年の「"http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4480058184/zu-22 パラサイト・シングルの時代」で「パラサイト・シングル」という概念を提唱した。しかし、それから5年後の現在、「なぜ親元に同居するのか」について別の考え方が必要とのことで書かれたのがこの本。
前著では、バブル崩壊直後の状況を元にしていたため、「裕福な暮らしをするために」と記述されていたが、今回は「親元でないと生活できない」世代が増えていることを明確にしている。
NHKスペシャルで放送されたフリーター漂流〜モノ作りの現場で〜で赤裸々にされたように、若年層の労働状況は燦々たるもので、パラサイトになるのもシングルになるのも仕方がない状況に思える。この番組をみたあと私はかなり暗い気持ちになったし、友人の意見も同様であった。
ちなみに、googleでフリーター漂流を検索すると、この番組での反響の多さが実感できる。
ということで、この本はお勧め。5-10ページ程度の短いエッセイを多数まとめた形式になっていて手軽に読めるのも良い。
あ、同じ著者の「希望格差社会—「負け組」の絶望感が日本を引き裂く」も買ったけど積読状態だわ...
■ 本 / 娘たちと話す 左翼ってなに?
娘たちと話す 左翼ってなに?、アンリ・ウェベール著、石川布美訳、現代企画室。
「サヨク」ではない「左翼」についての説明。 左翼の価値体系とは何か、それは右翼と何が違うのかが、きちんと書かれている。リベラルな人にはお勧め。
■ 本 / 企画力! ビジネス・プロデューサーになる50の方法
企画力! ビジネス・プロデューサーになる50の方法、横山征次著、講談社現代新書。
いいこと書いてあるんだけど、ちょっと理想が高いかなあ。 企画書の書き方、のような How to 本を期待すると期待はずれになると思う。まあまあ。
■ 本 / MBA式「無駄な仕事」をしない技術
MBA式「無駄な仕事」をしない技術、斎藤広達著、青春出版社。
よくあるMBA本。私にとっては既知の内容ばかり。 書いてあることは学生にも有効、というか学生時代に身に付けておかないとまずいように思うので、子供に読ませてみよう。まあまあ。
2005/02/26
■ mktemp
mataさんとこの話題。一時ファイル名を作成する領域を誰がどこに確保しておくのが正しいのか、ってあたりが一見妙な仕様の元なのかも。
しかしまあ、一時ファイルの扱いはセキュリティホールの温床なので、もうちょっと高レベルの関数がほしいところではある。
2005/02/25
■ 風邪
2/21ごろから風邪。吉浜さん宅に先週末にお伺いして、帰宅するときに 背中に重たいものを感じて寒気がしたのだが、もしかすると風邪ではなくて 別の何かなのだろうか。
吉浜さんがさびしがるといけないから、お帰ししないといかんなあ。
風邪の熱やだるさは減ったが、声が変になってしまった。困った。
■ 最近人気のメラ掲示板
メラ(genta)'s掲示板が最近人気のようだ。
ところで、webページの内容を監視し、変更があったらそれをタイムスタンプ付で記録しておくようなソフトってないかな。できればperlで書かれているといいんだが。 私的archive.orgが欲しいつーか。
2005/02/19
■ OIA勉強会
またしても飲んだくれる。財布に金が残ってない...
2005/02/18
■ Willcomのキャンペーン
Willcom(旧DDIポケット)で ゲット!EDGEなドメインキャンペーンという謎のキャンペーンをやっている。WillcomのPHSでパケット向けの契約をしている/新規加入する人に抽選でドメインをプレゼント、らしい。4月30日まで。よくわからんけど応募してみた。
2005/02/18
■ 謎の爆発音
花火のような落雷のような音が東から聞こえた(東南東ぐらいかな)。 雷かなあ。
2005/02/17
■ ぐるぐる / 大規模店舗とまちやーぐゎー
以下のblog。うすうす思ってたことをはっきり書かれると(先に書けない自分が)くやしい。
- コスト社会に必要な中小商店。大規模店舗が進出し、小規模店舗が潰れ、そして大規模店舗が去ったあとはどうなるのか。
- 縮み時代の始まり--歴史の変曲点にきた日本を考える。小樽の町は日本の未来か
- ビジネスってそういうものなのだとしたら頑張れる
■ ぐるぐる / デジタルハリウッド
デジタルハリウッドは大学を名乗るに相応しい存在か?(デジタルコンテンツ業界考)。切り込み隊長blog。「逆に言えば、そこが収益源泉であり、なるだけ外には触らせない?」の質問の回答は当り前と言えば当り前だが、つらい。
2005/02/16
■ ぐるぐる / 紅天女
特別企画公演紅天女。マジですか?
@parallel mindsで知りました。
2005/02/15
■ ぐるぐる / 2005年の衝撃トレンド・属性のコモデティ化(その2)
2005年の衝撃トレンド・属性のコモデティ化(その2)。面白い。
■ ぐるぐる / 伝統と誇るものに大した伝統はない
伝統と誇るものに大した伝統はない。御意。
■ アマゾン恐るべし...
アマゾン恐るべしつーか、誰がこういうのをアマゾンから買うのだろうか...
2005/02/13
■ PCdepot
OAシステムプラザ改めPCdepotに行ってきた。 前よりはいいかな。雑誌が無くなってる分だけ、他の展示が広い。 見通しがいいせいか在庫は少なめに感じる。
家から近いから時々は寄ってみよう。
■ 着うた
AirH"PHONE「AH-K3001V」で着うたもどきにチャレンジの通りやるとちゃんとできた。楽しい。音量合わせと切り出しが結構時間を喰う。
携帯の方は、携快電話11というソフトを買ったのだが、このソフトが以下略。 まあ、アドレスが拾えればいいと思って一番安いのを買ったのだけど。
2005/02/09
■ Opera8β
Opera のβ版に変更してから、タブ内にcloseボタンが表示されてて、 非常に使いづらかったのだが、ようやく対処方法を発見。 Tools → Windows で、Window handling を Advanced Opera workspace にすれば 7.x と同じような使い勝手に戻る。
poor usability in Opera 8の記事の批判はまったく正しいと思う。Opera-PukiwikiのOpera8のところにも解決方法がある。FAQだったりするのかな。
2005/02/08
■ iPod Shuffle
人気のiPod shuffleを使って こんなことをする人が...
いやー、確かにやればできるんですが...
2005/02/07
■ 天文台
ReichaNet IRCで聞いた話。石垣島に天文台ができるらしい。 星降る石垣島に今夏にも新天文台・惑星探査の支援に期待。いいことだ。口径1mってどれぐらいの性能なんだろうか。天文関係機関リスト地域別・国内からすると国内にある公開天文台としてはいい方みたいだけど。
そういえば昔NHKで「山のてっぺん天文台♪」って歌う番組があったなあ。 googleしたところでは「大きくなる子」という番組のようだ。
■ ぐるぐる
本・雑誌数千冊、アパート床抜け生き埋め…56歳重傷(読売新聞)。あまり他人事ではない。コミックスだけで4700冊ほどあるんで...全部だと1万近いかも。
- 存在の耐えられない重さ…大量の雑誌で床抜け公務員重傷(zakzak)
2005/02/06
■ 醤油
醤油が切れそうである。
我が家は、もっぱら「尚代」(伊藤商店のたまり醤油)と「白醤油」(日東醸造の小麦だけを使った醤油)を使っている。以前はパレット久茂地内のリウボウ地下で売っていたのだが、最近、そこには置いていなくて入手困難である。
白醤油は醸造元の日東醸造か楽天の通販でも買えるのでまだいいんだが、尚代が手に入らない...
同じ伊藤商店の「傳右衛門たまり」なら通販しているところが何社かあるようだが...
■ 買い物メモ
買い物メモを追加。
2005/02/05
■ 本 / 「書く力」が身につく本
「書く力」が身につく本—手帳とメモからはじめる自己表現の技術、福島哲史著、PHP文庫。
「文章を書く」ということを軸に、書くことで得られることや その他の仕事のノウハウを書いた本。 最初に刊行されたのが1993年でインターネットがまだ普及していない ころであり、電子メールへの言及がないのが残念。
ただ、この本の中でのワープロやFAXの効用を読んでいると、 PCを得たことで引き換えに失ったことが多いようにも思った。
この手の本は、その性格上、「目的志向で作業をする」ことを 勧めがちでそこがちょっとだけ気になった。 でもまあ、お勧めだと思う。
■ 本 / 論理思考の鍛え方
論理思考の鍛え方、小林公夫著、講談社現代新書1729。
オビの文句は『「お受験」からロースクールまで 試験に通る「思考力 」とは?』。その通りの本。 さまざまな問題を元に、その問題はどのような意図で受験者のどのよう な能力を判断するために記述されているのか、どう回答すべきかを書い ている。若干強引な部分もあるが、面白い。
■ 本 / 学力をつける100のメソッド
学力をつける100のメソッド、陰山英男著、和田秀樹、PHP研究所。
最近、書店でよく見かける 陰山メソッドの一冊。
子供の教育上よくある100の質問に 陰山氏と和田氏が回答していくという体裁を取っている。二人の教育間の違いもあり、面白く読める。
しかし、実際この本を元に教育するのは大変だろうなあ。 むしろ、子供に読ませて自分で考えさせたほうがいいように思う。
■ 本 / 人間性の進化史—サル学で見るヒトの未来
人間性の進化史—サル学で見るヒトの未来、正高 信男著、NHK人間講座、日本放送出版協会。
携帯電話やさまざまなコミュニケーションの道具を使うことで、 我々人間は、進化の途上で得た何かを失っているのではないか、 という本。面白い。
元々、NHK人間講座のテキストとして書かれているため、 読みやすいわりには比較的高度な内容が書かれている。
2005年1月24日の記事で紹介したネット王子とケータイ姫—悲劇を防ぐための知恵と併せて読むことをお勧めする。
■ 本 / 越境としての古代〈2〉
越境としての古代〈2〉、越境の会編集、同時代社。
室伏志畔の提唱した幻想史学の手法を元に、8人の著者が九州王朝の真実に迫る本。越境としての古代の続巻。
九州王朝説を前提にしている上に、幻想史学という手法を使っているため、前提条件に理解がない人にとってはトンデモにしか思えない本だと思う。逆に私のように九州王朝説に肯定的で、幻想史学という手法に(100%賛成はしないまでも)利点を見出せる人であれば、非常に面白く読むことができると思う。
九州王朝説については、提唱者である 古田武彦氏の著書を読むことをお勧めする。特に 「失なわれた九州王朝」・「盗まれた神話」が古典でありお勧めなのだけど、残念ながらamazonにもbk1にも在庫がないようだ。Webに九州王朝とは…?という記事があるのでご参考まで。
あるいは、中山千夏氏の新・古事記伝・神代の巻をお勧めする。
■ 本 / 使える!受験英語リサイクル術
使える!受験英語リサイクル術、尾崎哲夫著、PHP新書。
受験の時に勉強した英文法をリサイクルして、英語上達に役立てよう、という本。読んでみると、習ったような気もする英文法が次々でてきて、懐かしい。でも細かいところは全然覚えてないなあ。関係副詞なんてあったのか(^^;
面白いけど、これで上達するのだろうか。 受験生のように常に持ち歩いて英文法を覚えるのにはいいかもしれない。
■ 本 / 子どもに教えたくなる算数
子どもに教えたくなる算数、栗田哲也著、講談社現代新書。
算数の良問を、図を駆使して説明し、面白さをわからせる本。 面白いし、お勧め。 面白いけど、こういうのは昔は雑誌に載ってて、 知らず知らずのうちに勉強できたような気がするなあ。
小学校高学年の子なら読んで面白がれると思う。
■ 本 / 心を商品化する社会—「心のケア」の危うさを問う
心を商品化する社会—「心のケア」の危うさを問う、小沢牧子著、中島浩籌著、洋泉社 新書y。
「癒し」「心のケア」という言葉で、心を商品化することが進んでいるが、それは本当に我々のためになっているのだろうか? 社会の問題を個人の責任にしてはいないか? といった問題提起の本。考えさせられる本。
「心の専門家」はいらない」と一緒に読むことをお勧めします。
2005/02/02
■ AH-K3001V / バージョンアップ失敗
バージョンアップ失敗しました。 書き換えモード以外では、電源入りません。 バージョンアップしようとしても53%で、画面点滅になります。 しくしく。
明日は京セラに電話だなあ...
2005/02/01
■ 本 / マンガでわかる売れる営業マン 売れない営業マン
マンガでわかる売れる営業マン売れない営業マン—ちょっと「できないフリ」がお客の心をつかむ、馬渕哲著、南条恵著。PHP文庫。
著者の馬渕哲氏は、入りやすい店売れる店などで流行る店の条件をアクションという観点から分析していて、私はその分析の鋭さに納得したものだ。 その著者による営業の分析ということで期待しながら読んだ。 期待に違わず面白い。お勧めします。
高橋伸夫の虚妄の成果主義もそうだけど、過去、いわゆる日本的システムで、うまくいっていたものに対して、きちんと説明した本が出てきているのは、バブル崩壊後のグローバリズムのゆり戻しのように感じる。そういえば明治以前の江戸期の本も増えてるし。
■ 本 / できる社員は「やり過ごす」
できる社員は「やり過ごす」、高橋伸夫著、日経ビジネス人文庫。
以前読んだ虚妄の成果主義と同じ著者の本。虚妄の成果主義と同じく日本的年功制の良さを説く。 お勧め。
■ 本 / 寝ながら学べる構造主義
寝ながら学べる構造主義、内田樹著、文春新書。
本村先生のWebで見て面白そうだったから買ってみたのだが...難しい。とても寝ていては読めない...
■ 本 / 40歳からの仕事術
40歳からの仕事術、山本真司著、新潮新書。
「子曰、...四十而不惑」と、あの孔子がわざわざ言ったということは、 大抵の人間は40歳になると迷う、ということであろうか。 この本も、40歳で迷う主人公を、一足先に転職しコンサルタントをしている元同僚が 導いて、再度やる気を出させるまでの本。かなりMBA臭いし、筋書きもイマイチなのだが それでも面白いと思う。 迷ってる人にはいいんじゃないかな。
■ 本 / 12歳からのエゴグラム—学校で生きぬくための心理学
12歳からのエゴグラム—学校で生きぬくための心理学、高橋久著、ぺんぎん書房。
心理テストの結果を元に自分の性格を把握して、より良く成長するための 材料にしよう、という本。昔の私なら素直に読めただろうけど、 今では、「問題を個々人の内面に押し込み矮小化する」ための本に思えてしまう。 悪い本ではないと思うが、先に下記の本を読むことをお勧めする。
- 「心の専門家」はいらない、小沢牧子著、新書y。
- 心を商品化する社会—「心のケア」の危うさを問う、小沢牧子著、中島浩籌著、新書y。