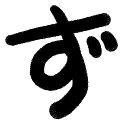2005/01/28
■ 婆さんセット
とある理由で、 edy の使える店を探したら、以下のような店が見つかった。
「○○ホテル バーサン セット」
何! 婆さんセット?
お年より優先なのか。さすが沖縄。それにしても大胆だなあ。
と思ったら、バー サンセットだった。
2005/01/27
■ メモ
東京ビデオフェスティバル2005にnatsukiなHIKOさんの作品「だるまさんがころんだ」が出展されているそうだ。 あとで見よう。
2005/01/24
■ 本 / 物理と数学の不思議な関係
物理と数学の不思議な関係—遠くて近い二つの「科学」、マルコム・E.ラインズ著、青木薫訳、 ハヤカワ文庫 NF—〈数理を愉しむ〉シリーズ (295)、
原題は On the Shoulders of Giants 「巨人の肩の上で」。 物理学が如何に数学という巨人の肩に乗っているかを書いた本。 ほんと、物理を学ぶと、どうして都合よく数学が先にあるのか疑問に思うし。 数学・物理が好きならお勧め。
■ 本 / システム手帳新入門
システム手帳新入門!、舘神龍彦著、岩波アクティブ新書。
2000年代のシステム手帳の入門書。80年代のブームのときの本では古いと思う人に。 変に宗教がかってないところがいい。まあお勧め。
■ 本 / ネット王子とケータイ姫—悲劇を防ぐための知恵
ネット王子とケータイ姫—悲劇を防ぐための知恵、香山リカ著、森健著、中公新書ラクレ(155)。
最近の子供の、携帯電話やインターネットの使い方を、大人に教えるための本。 面白い。上記のようなことをちゃんと知りたい人にはお勧め。
■ 本 / 「不自由」論—「何でも自己決定」の限界
「不自由」論—「何でも自己決定」の限界、仲正昌樹著、ちくま新書。
自由と不自由に関する論説。面白いけど、よくわからない。 まあ、この人の本はいつもそうか。
■ 本 / 科学する麻雀
科学する麻雀、とつげき東北著、講談社現代新書。
筆者はネット麻雀である東風荘で数千局の麻雀を打ち、データを採取し、統計的に正しいであろう麻雀の打ち方を研究している。研究はとつげき東北システマティック麻雀研究所でも公開され、今回、筆者の成果をまとめた本が出版された。
麻雀雑誌で言うところのデジタル麻雀とは深みがまったく違うレベルに達している。 筆者が「いずれは、本書の内容をしらずして麻雀を語ることのできない日が来るでしょう」と豪語するだけのことはある。 非常に面白い。 桜井章一とは違う意見もあるが、どちらも面白い。麻雀好きな人にお勧め。
■ 本 / 論破できるか!子供の珍説・奇説—親子の対話を通してはぐくむ科学的な考え方
論破できるか!子供の珍説・奇説—親子の対話を通してはぐくむ科学的な考え方、松森靖夫著、ブルーバックス。
「夏は地球が太陽に近づくから、暑くなるんだね」といった、 正しいようで間違っている珍説・奇説を正しく解説する本。 昔はこの手の本は結構あったような気がするが最近は見かけないなあ。 お勧め。もうちょっと説明が細かいといいんだが、高望みか。
■ 本 / そのバイト語はやめなさい—プロが教える社会人の正しい話し方
そのバイト語はやめなさい—プロが教える社会人の正しい話し方、小林作都子著、日本経済新聞社。
「よろしかったでしょうか」が気になる人は読むべし。気にならない人も読むべし。 この本が書くところの「社会人の正しい話し方」には賛同できない部分も わずかながらあるが、それを引いてもお勧めの本。
2005/01/23
■ 七輪 / あさり と しちゃも・きびなご と えりんぎ
最近、我が家ではあさりを七輪で焼いて食うのが流行している。
 しらをきるあさり
しらをきるあさり
 火責めにあうあさり。「吐け、吐くんだ」
火責めにあうあさり。「吐け、吐くんだ」
 事態を見守る茄子とえりんぎとししゃも
事態を見守る茄子とえりんぎとししゃも
 「あっしがやりました」ぱかっ
「あっしがやりました」ぱかっ
 「ほれほれ、仲間はとっくに白状したぞ」
「ほれほれ、仲間はとっくに白状したぞ」
 「おゆるしをー」次々白状するあさり逹
「おゆるしをー」次々白状するあさり逹
 その後できた貝塚
その後できた貝塚
2005/01/22
■ OIA勉強会
つらつらと、いろんなことを話す。 これで参考になるのだろうか。
2005/01/05
■ 計算尺
とある古い文具店(営業40年だそうだ)で、計算尺を発見。 HENMI No.2664S と No.2634 (ポケット用革ケースつき)。 いやー、探せばあるもんだな。