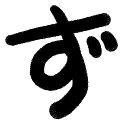2008/05/30
■ ぐるぐる / FRB議長ゲーム
「米SF連銀サイトの『FRB議長ゲーム』を試してみたら…」(本石町日記)。 アメリカ連邦銀行の議長になったつもりで、金利を操作して物価の安定と雇用の確保を図るゲーム。 議長として再雇用(reappointment)されるのが目的。 そのためには最終的に金利を2%ぐらいに誘導する必要がある。 インフレターゲット政策を取っているわけだ。
結構面白いけど、ある程度金融政策を知らないと楽しめないかも。
2008/05/29
■ 無線LAN / FONのやることはわけがわからん
「FON_APからFON_FREE_INTERNETへ表示変更のお知らせ」。 いつの間にか勝手にSSIDが変わっているという話。 我が家のFONのSSIDも変わってた。なんじゃこれ。
■ もやしもん / グッズが増えてる
かもされてる人が多いのかグッズが増えてる。 携帯クリーナーは ちょっと欲しい。さすがに除菌クリーナーではないっぽい。
- STUFFED Collection もやしもん もーいっちょ!かもすたっふぃんぐ A・オリゼー(コスプレver.)
- もやしもん 菌携帯クリーナー(オリゼー&ソーエ)
- もやしもんソフトステージ〜菌劇場ミニ〜
ircで情報もらった。
2008/05/28
■ CD / 昔のCDがいろいろ復刻されてるのだな。中森明菜とか
中森明菜 とか、八神純子 とか。紙ジャケット仕様らしいけど、手に入るだけありがたい。 中古探してもなかなかなかったりするんだよね。
「ANNIVERSARY」など数枚を購入。
2008/05/27
■ 雑誌 / 日経サイエンス2008年7月号 - 切った指が再生する話
ちょっと前に「驚きの最新治療─パウダーをつけただけで切断した指が完全に生える」(らばQ)という記事が話題になっていた。記事の内容がうさんくさかったので、それ以上はちゃんと調べなかったんだけど。
定期購読してる「日経サイエンス2008年7月号」が届いたのでそれを読んでたら、指の再生の話題にでくわした。iPS細胞絡みで再生医療の特集を していて、その中の一記事。「失われた手足を再生する」というタイトルで サンショウウオでは再生が可能なのに人間ではなんで出来ないのかという記事。
読み進めていくと、人間の場合でも指先は再生すること、傷口を縫い合わせると再生できなくなってしまうこと、実際に再生した例があることなどが掲載されていた。うーむ。実は らばQの記事は正しかったのだな。思いこみが良い方向に裏切られた。
参考: 「骨欠損を伴う指尖部損傷:プラスモイスト使用例」というページを見つけた。写真がナマナマしいので、そういうのに弱い人は見ないほうがいいかも。
2008/05/23
■ Amazon / Amazonを倉庫代りにしてた人
2chの「Amazonを倉庫代わりにしていた転売厨終了のお知らせ」スレのネタ。 ITmediaにも「"転売ヤー"に、Amazonが最後通告 Amazonで商品確保、ヤフオク空売り」。
仕組みの裏を突いて儲けていた人の話。しかし頭いい人っているんだなあ。 どうやったら、こういうのを思いつけるんだ?
2008/05/22
■ ぐるぐる / なんたら-users.jp というドメインが流行っているようだが
perl-users.jpに始まって、 php-users.jpやら ruby-users.jpなどが出来てるんだけど、 これドメイン屋の陰謀じゃないのか? jpドメインは結構な値段するし。
2008/05/19
■ ぐるぐる / H5N1型という"敵"に日本が採るべき策
「H5N1型という"敵"に日本が採るべき策」(SAFETY JAPAN)。 新型インフルエンザについてのまとまった記事。一読すべき。
2008/05/15
■ 今日は何の日 / 5.15は復帰の日
復帰運動のころは、4.28も大事な日だったけど、最近あまり聞かないな。
■ Amazon / アマゾンのビジネスモデルって...
Amazonのやってることって、販売関連にしてもAmazonS3/EC2にしても、 とてつもないことって感じではなくて、やればできることを大規模にやってるだけなんだよね。 それがまあ凄いと思う。
日本の他の書籍販売サイトは、たぶん従来の出版業とか取次とかのしがらみがあって、 ああなってると思う。そこがAmazonとの違いと。
ここまで書いて思ったんだけど、これって音楽会社とiTunesの差に似てるな。 従来仕組みの延長ではなくて、外部から見て利用者に適切な解を与えてるところとか。 だとすると、他の業界でしがらみがあるところを探せばネタがあるわけだ。 それはどこだろう?
- 参考:「日本の「IT技術」はまだまだ期待があるけど、「IT産業」はダメなんじゃないかって気がする」(おごちゃんの雑文)
2008/05/14
■ 文字コード / 中国の地震の話なんだけど
地震が起きた場所の紹介が「ブン(さんずいに文)川県」となっている記事が多い。 Unicodeに文字はあるので、実体参照を使えば「汶川県」のように表示できるはず。 ちなみに 汶 だ。
追記: 使ってるフォントによっては見えないかも。
■ 迷惑メール処理 / scmail に大きなファイルを喰わせると...
迷惑メールの振り分けには「scmail」を 使っているのだけど、学習の際に添付ファイルがついているような大きなファイルを 喰わせると、メモリをもりもり消費してしまう。 先頭の数10KBぐらいを処理すれば実用上充分なはず。 そのうち改造しよう...
ad hocな解決策として、学習用メールの入ったディレクトリを ls -lS|head して、 サイズの大きなファイルを除去した。とりあえず、これで逃げておこう。
2008/05/13
■ 本 / Googleを支える技術 巨大システムの内側の世界
Googleを支える技術 巨大システムの内側の世界、西田圭介 著、技術評論社。
最近、会う人ごとに進めている本。コンピュータに関わるエンジニア必読。 これだけの本を母国語で読めるというのは幸せだと思う。 そして、googleとの格差を思う。
ただ、まあ、GoogleAppEngineやらAmazonEC2が使えるので追いつくのはそう困難ではないかもしれない。資源の投入さえできれば。
ということで、今年一番のお勧め本です。
追記: 2008/5/14現在、amazon売りきれ中。楽天ブックスは在庫あり。
2008/05/12
■ Google / クラウドコンピューティングのカンブリア爆発 と MapReduce
コンピュータの世界で何か新しいことが始まる時には、 簡単ながらも多様な実装が爆発的に現れて、 いろいろな可能性が試されたあとに、淘汰され、ごく少数の実装が残ることが多い。 生物学で言うところのカンブリア爆発に似た現象だ。
クラウドコンピューティングの世界でも同じことが起こりつつあるようで、 MapReduceの再実装がぽつぽつ出てきている。
- MapReduce(Hatena::Diary::naoya) - はてなの naoya さんによる perl での実装
- RubyでえせMapReduceもどきを作ってみた。 (rubyneko)
- Thread Base MapReduce(moratorium) - 2007/1に既に試した人がいる。C++
- Writing An Hadoop MapReduce Program In Python (Michael G. Noll) - 分散OSであるHadoop上での実装
Googleと比べると全然クラウドじゃないんだけど、それは大昔の Fortran と比べた Tiny Basic とか、 大型機と比べた 8bit マイコンとか、そういう感じ。そこがまた面白い。
さて、この先どうなるのかが楽しみである。GAME言語みたいな実装が見てみたいものだ。
2008/05/07
■ Opera / Speed Dial の数を増やす
「Speed Dial のエントリを増やす」(A blog? with Σαιτω)
最近の Opera にはSpeed Dial という機能があって、CTRL+T等で新規のページを 開いた時に、何もない空白の画面ではなく、予め指定しておいたページの サムネールを表示し、選択できる機能がある。 最初は、ブックマークでいいじゃん面倒臭い、と思ってたのだが 使ってみると結構便利。文字ではなくてサムネールで選べるところが良い。
唯一の問題は選べるページの数がデフォルトでは9個までだったこと。 上記の記事はこの数を増やすための設定についての情報。 とりあえず16個にしてみた。これは便利だ。
■ Google / Google App Engine で Python 2.5 が必要なわけだが
常用している環境(CentOS5とか4)は Python2.4ベースで、Google が 配布しているSDKが動作しない。CentOS に限らず 最近の Red Hat 系の Linux は、 システムの基本部分(パッケージ更新とか)に Python を使ってるので、 下手にバージョンを上げると はまりそうな気がする。
そのせいか、巷のGoogleAppEngine紹介サイトでは、Python2.5以上を使ってるOSを使うか、/usr/local/bin に Python 2.5 を入れるか、 別マシン(VMwareとか)で動作させるか、 Windowsを使う例が紹介されている。 そこまでやるのも面倒だなといろいろ考えていたのだが...
AmazonEC2使えばいいんじゃね? ってのを思いついた。AmazonEC2では Python2.5以上を使ってるディストリビューションのAMI(OSイメージファイル)が提供されているので、これを使えば あまり苦労せずに試せそう。$0.1/時間なので10時間使って$1だし。 本格的に開発する気になったら、別に環境作ればいいわけだ。
ということで、ubuntuあたりのAMIを検索中。 GoogleAppEngineのSDK入りAMIがあるともっと良かったんだけどさすがにそれは無いみたいだ。
■ Amazon / OpenSolaris が AmazonEC2 の AMI で提供されている
「OpenSolaris on Amazon EC2」(Amazon Web Service)。
OSの試用をするのが楽になるのはいいことだ。 今後は、特にサーバー向けOSは、AmazonEC2で提供/試用されることが増えるかも。
2008/05/01
■ Amazon / AmazonS3 でログを取る
AmazonS3でログを取る方法を探してたんだけど、ようやく発見。 Programming Amazon Web Services: S3 and Ec2のChapter 3、「Server Access Logging」に方法が書いてある。
それを参考にperlで試したけど、うまくいかんぞ (-.-;
結局、s3safeを
使うと簡単に設定できる、というところまでは わかった。
s3safeで設定してみたけど、ログ記録されてないなあ。
設定もACLもよさそうに見えるんだけど。
追記: あとで見たらちゃんとログが残ってた。指定したbucket(ディレクトリ)に、prefix-YYYY-MM-DD-hh-mm-ss-なんちゃら というファイル名で格納されている。apache 等で利用されている common log format に似ているので変換を書ければいろいろ使えそう。 試験用サイト「s3.zu2.org」のログを見た感じでは、クローラーのアクセスが結構多い。これが課金の大半かも。とほほ。
AmazonS3関連はWikiのAmazonS3にまとめてます。