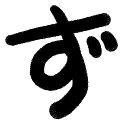2006/05/31
■ ニュース / 中国から日本のメールサーバー内のメールが受信不能に
中国から日本のメールサーバー内のメールが受信不能に(Internet Watch)。
今月のOIAの勉強会でも、中国からのWebアクセスが制限されているという話が 出ていたが、ついにメールまで制限かかったようだ。どんどん巨大イントラネット化する中国....ついでに、OB25も制限して欲しい。
2006/05/24
■ 本 / ちゃんと話すための敬語の本
ちゃんと話すための敬語の本 、橋本治著、ちくまプリマー新書 (001)。
敬語の使い方、の本ではなく、敬語とはそもそも何ぞやということを わかりやすく書いた本。まあ、橋本治なのですが、いい本だと思う。
特に、現代の敬語は「尊敬」を表すというよりは「距離」を表すということを 明確に言い切っているのが良い。 お勧めします。ちくまプリマー新書なんで子供さんにもいいかも。
■ 本 / 漢文の素養 誰が日本文化をつくったのか?
漢文の素養 誰が日本文化をつくったのか?、加藤徹著、光文社新書。
卑弥呼の昔から現代に至るまでの、日本における漢文の歴史。 ややもすると、日本語と中国語は独立していて、テクニカルタームとしての 漢語を輸入しただけのように思い込んでしまうのだが、 漢文や漢文訓読が日本語に与えた影響は大きい (明治期の翻訳文が現代日本語に与えた影響のように)。
漢字や日本語に興味を持つ方にお勧めします。 漢文が面白くないと思ってる人にも。
■ 本 / 満州と自民党
満州と自民党、小林英夫著、新潮新書。
「満州というよりは満鉄の人脈」が戦後体制(55年体制)で何を行ったのかを 人の面から描いた本。人工国家満州でできなかった理想郷を戦後日本で 創ろうとした、という視点は新鮮で面白い。
満鉄はイギリスの東インド会社と同様の植民地会社である、というのも 指摘されるまで気がつかなかった(忘れてた?)。
満州や戦後体制に興味を持つ人にはお勧め。
■ 本 / はじめての部落問題
はじめての部落問題、角岡伸彦著、文春新書。
部落問題に対する部落出身者による入門書。 堅苦しくなく、歴史から現状までを学べます。非常にお勧め。
しかし、部落問題って「部落の問題」じゃないんだよな。 「パレスチナ問題」が「イスラエルの問題」で 「沖縄の基地問題」が「日本政府の問題」であるように。
■ 本 / シリーズ心の哲学〈2〉ロボット篇
シリーズ心の哲学〈2〉ロボット篇、信原幸弘編集、勁草書房。
私が興味を持っている事項の一つに、人工知能におけるフレーム問題がある。本書はフレーム問題も含めて、認知哲学についての論文を集めた本である。
本書でもっとも興味を引いたのは最後の論文で、「そもそも心の捉え方自体が社会制度を反映している」とか「心と外部の境界はどこか」という当たり前のようで分かってない問題を指摘している部分である。ここを読むだけでもこの本を買う価値はあると思う。 シリーズの別の巻も買うことにした。
認知心理学とかAIに興味を持ってる人にお勧め。
そういえば、最上の日々の意識とは何なのかについての私見も面白い。
■ 本 / 『古史古伝』異端の神々 太古日本の封印された神々
『古史古伝』異端の神々 太古日本の封印された神々、原田実著、ビイングネットプレス。
古史古伝に出てくる神々をネタに、それぞれの古文献の成立過程や 意義について書いた本。古史古伝の入門としても悪くないかもしれない (佐治芳彦よりはいいだろう^^;)。
この本でも書かれているけど、吾郷清彦 が大陸書房から出版した古事記以前の書というのはインパクトの大きい本だったのだなあ。私もこれでこの世界に踏み込んだわけだし。
著者の原田実 はアカデミックな人なので、むやみに古史古伝を持ち上げることもなく、淡々と記述されている。 興味がある人にはお勧めかなあ。
原田さんが管理人をしているmixiのコミュニティも面白い。
■ 本 / マンガの深読み、大人読み
マンガの深読み、大人読み、夏目房之介著、イーストプレス。
夏目房之助 は、以前からマンガ論を公表しているマンガ評論家だが、彼のマンガを見る姿勢が変わる時期の文章を集めたのが本書。 視点の変化が日本やマンガの変化に重なっていて、同時代を生きてきたものとして 面白く感じられた。マンガ論に興味があるならお勧めかな。
■ 本 / 実戦麻雀の急所—デジタルVSアナログ
実戦麻雀の急所—デジタルVSアナログ、バビロン編集、新・麻雀覇王ブックス。
麻雀の対局者に、互いに相手の声が聞こえないようにヘッドホンをを装着し音楽を流した上で、対局中に考えたことを喋らせて参考にする、という記事を時々麻雀専門誌で見かける。カストリ雑誌よりは長生きした(復活後の)近代麻雀、とかプロ麻雀に時々そのような記事がある。
本書は、半荘一局をヘッドホン麻雀で打った過程をそのまま載せ、各局ごとに解説を付けた書である。
着眼点はいいのだが、解説をもうちょっと工夫した方が良かったのではないか。 第三者ではなく敢て当事者に解説をつけてもらうのも良いし。
しかしまあ、いずれにせよ、 とつげき東北氏の科学する麻雀を先に買うべきという結論に変わりはない。本書も悪くはないのだが。
ちなみに本書は、毎日コミュニケーションズから出ている。 最近の毎日コミュニケーションズは結構面白いというか、とんがった本が 出ていて目を離せない。
2006/05/18
■ 録画録音補償金問題
補償金問題セカンドステージ。以前、iPod課金で話題になった録画録音補償金の話。こんどはPCのハードディスクも課金対象にしたいとJASRACは言いだしてきたらしい。 何を考えているのだろうか。気になる人は上記の記事と、 パソコンも私的録音補償金の対象にを参照のこと。
2006/05/17
■ 安いソフト使用記
安いソフト使用記に、eTrustイージーアンチウィルス と携帯マスターSmart2の記事を追加。
■ 映画 / 「おいでよ どうぶつの森」映画化決定
「おいでよ どうぶつの森」映画化決定。ということで、 Nintendo DSの大人気ゲーム、おいでよどうぶつの森が、映画化されるらしい。2006年12月公開予定。
あらすじ: 一見、のどかな、どうぶつが闊歩する森に言葉巧みに連れ込まれた主人公は、 悪徳商店主たぬきちに騙されて多額の住宅ローンを背負ってしまう。 ゴミ箱漁りで得た品物や魚や果物を搾取されながらも、 主人公はコツコツと借金を返していく。 悪徳保険金詐欺や贋作美術商にも負けず、 日銀のゼロ金利政策のおかげで幸いにも破綻もせず、 無事に借金を返済したのも束の間、 主人公から搾取した金で店を豪華にするのが野望の 悪徳たぬきちは主人公にさらなる借金を押しつけるのであった...
という映画ではないよなあ、きっと。 どんなストーリーなんだろう。
2006/05/16
■ サーバー不調
んー。何が原因かよくわかんないなあ。 PMTU discoveryあたりか?
MTUいじったら改善したんで、PMTU discoveryが怪しい。でもなんで?
2006/05/12
■ Opera / Opera9 Weekly Build 272
Linux版Opera Weekly Build 272で、日本語入力の問題が解消された。よかった。
2006/05/10
■ 日経の謎
TDR入場者数が初の2年連続減少・USJは3%増 トレンド-速報:IT-PLUS。
TDRって何だよって思って記事を読んだら、ああああ。
これ4月4日の記事なんだよなあ。1ヶ月以上も誰も気がつかなかったのか?
追記:識者に教えていただきました。なるほど。
たしかTDRって東京ディズニーリゾートのことだったと思います。
TDR=ディズニーランド+ディズニーシー
追記: 2006/06/02 時点で、やっぱりああああ。
■ 無さそうでやっぱり無いもの
「もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング」の攻略本。
もちろん、「脳を鍛える大人のDSトレーニング」の攻略本もない。
細菌撲滅のスコアの計算方法のページ、どこかにないかなあ。
おまけ: YouTube:おばあちゃん偉すぎ
2006/05/09
■ 蛍族嫌い
だからさー、君んちはクーラー入っててフィルタされているかもしらんけど、 君がベランダで吸ってるタバコの煙がうちに入ってくるのは勘弁して欲しい。
2006/05/08
■ ドメイン / レジストラの選び方
ircネタ。
23:11 ドメインねえ 23:11 いろいろ使っててどれも特にトラブルはないんですが 23:12 「更新の通知がSPAM扱いされにくい」ところがいいですね(^^;
2006/05/07
■ どうぶつの森
娘1が貴重種の花畑をこさえたので、記念。
2006/05/06
■ 雑誌 / メロディ隔月刊に
白泉社の少女向け雑誌は 「LaLa」も「花とゆめ」も腐女子 系というか、ライトノベル のコミック版みたいなものに成り下がってしまって読む気がなくなっていた。「メロディ」だけは昔の「花とゆめ」のような雰囲気が 残っていて良かったのだが、今どき、この雰囲気では成り立たないのだろうか...
元々、白泉社の雑誌ってマニア系ではあるんだよなあ。いまは亡きアスカと双璧というか。
隔月刊になっても、 「大奥」と「秘密」が連載されているうちは大丈夫だろうが、この2つがなくなったらやばいな。ちなみにこの2つはSFとしても良質。お勧め。
次に読む雑誌を物色せねば...
2006/05/03
■ 4月に読んだ本
うーむ。またしても書くのが翌月になってしまった。 バーコードリーダーかなんかで簡単に書ける仕組みにしないとダメだな...
■ 本 / 日本の漢字
日本の漢字、笹原宏之著、岩波新書。
日本の国字やJISの幽霊文字からアジアの漢字文化圏に至るまで、 日本の漢字についての解説。非常にお勧め。
追記: 筆者によるイベント「日本生まれの漢字たち」の講演メモが「日本生まれの漢字たち」(作業メモとか考えた事とか)に掲載されている。
■ 本 / 究極の文房具カタログ【マストアイテム編】
究極の文房具カタログ【マストアイテム編】、高畑 正幸 (著)ロコモーションパブリッシング。
TV東京の「全国文具通選手権」3連覇中の筆者の自費出版本(同人本)を 底本に加筆修正した本。
よくある文具本は、高級万年筆や高級文具をずらずらと掲載して 欲望を煽るものが多いが、この本は違う。 最初に紹介されているのは、105円のPILOT Vコーン。 あとも手ごろな値段で、使う価値のある文具が紹介されている。
この本も非常にお勧め。 仮にこの本を読んで欲しくなっても、財布はあまり痛まないし :)
■ 本 / と学会年鑑Yellow
と学会年鑑Yellow、と学会著、楽工社
毎年出版されている「と学会」の本。 と学会については「と学会公式ホームページか、と学会を参照のこと。
この手の本が好きなら買ってもいいと思います。
■ 本 / 京ぽん2必殺テク—音声&ネット新定番端末 京セラ「WX‐310K」を究める本
京ぽん2必殺テク—音声&ネット新定番端末 京セラ「WX‐310K」を究める本、スレアレ著、しげ著、二流著、WINDY Co.編集、memn0ck、ふぇちゅいん、アスキー。
WillcomのPHS WX310K の使いこなし本。同機種を持ってるなら買う価値はあると思う。
■ 本 / 千円札は拾うな
千円札は拾うな、安田佳生著、サンマーク出版。
いわゆる成功本。タイトルに惹かれて買ったが、、あまり納得できなかった。 おすすめしません。
■ 本 / こんなにヘンだぞ!「空想科学読本」
こんなにヘンだぞ!「空想科学読本」、山本弘著、太田出版。
柳田理科雄氏の空想科学読本 シリーズは、ウルトラマンやマジンガーZなどを科学的に解析するとトンデモになるという 内容の本で、シリーズ化されてかなりの部数が出ている。
しかし、その解析自体がデタラメで科学にもSFにもなっていないという指摘を しているのが本書である。
目から鱗。すっかり騙されていましたよ、私。 ということで、SF好き、科学好き、特撮好きな人にはお勧め。
■ 本 / 榊涼介&林正之のマルチプレイ三昧
榊涼介&林正之のマルチプレイ三昧、榊涼介著、林正之著、fukkan.com。
「電撃あどべんちゃーず」誌の連載記事の書籍版の復刻版。
さまざまなボードゲームやカードゲームの解説+漫画。 漫画はあまりゲームの参考にならない(^^; のだが、解説はためになる。 この手のゲームが好きな人にはお勧め。
■ 本 / 土田システム-麻雀が強くなるトイツ理論
土田システム-麻雀が強くなるトイツ理論、土田浩翔著、毎日コミュニケーションズ。
トイツ場に的を絞った麻雀戦術書。書いてあることは、まあ、そうかもしれないけど、 科学的じゃないんだよなあ。オカルトあるいは結果論と言われてもしかたない。
先に、とつげき東北氏の科学する麻雀を買うべき。