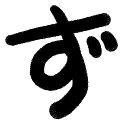2006/03/27
■ 安いウィルス対策ソフト
安いソフト使用記に、ソースネクスト・ウイルスセキュリティと、イーフロンティア・ウィルスキラーの話を追加。
2006/03/26
■ 本 / やっぱり欲しい文房具
やっぱり欲しい 文房具 ~ステイショナリー評論家がえらんだ普段使いの傑作たち、土橋正著、技術評論社。
よくある文房具本。これを読んだあとに安木屋あたりにいくと散財確実 :)
しかし、みんな、万年筆が好きだよなあ。なんでだろ。
■ 本 / 経済特区・沖縄から日本が変わる
経済特区・沖縄から日本が変わる、松井政就著、光文社。
なんというか、タイトル通り。特に新しいことは書いてない。 沖縄が外からどう見られているかを知りたいなら、買ってもいいかも。
■ 本 / アンダーグラウンドビジネス最前線
アンダーグラウンドビジネス最前線、夏原武著、江建著、日名子暁著、李策著、鈴木智彦著、洋泉社。
タイトル通り。そういうことに関わらないために読むべし、かなあ?
■ 本 / 経済学的思考のセンス
経済学的思考のセンス—お金がない人を助けるには、大竹文雄著、中公新書。
まあ、いわゆる経済学入門。悪くない。
でもなあ。経済学の悪いところは時間軸が無視されていることか。 我々は長期的にはすべて死んでいるのだし。
■ 本 / 鉄を削る
鉄を削る-町工場の技術、小関智弘著、ちくま文庫。
プロあるいは職人はこうあったのだろう。私もこうありたい。
■ 本 / 楼蘭王国
楼蘭王国—ロプ・ノール湖畔の四千年、赤松明彦著、中公新書。
シルクロード、といえばNHKのNHK特集_シルクロードである。まだ、私がTVを見ていたころ、NHKが放映していた浪漫な番組。 いやー、これで中央アジアというかロプノール近辺のことがかなり好きになったわけだ。 最近は、新シルクロードを放送している。
ということで、シルクロードあたりが好きな人にはお勧め本。 楼蘭がいかなる土地であったか、漢や他の国との関係など、 当時を偲ばせる本である。お勧め。
■ 本 / 歴史から読み解く英語の謎
歴史から読み解く英語の謎、岸田隆之著、奥村直史著、早坂信著、教育出版。
小学校で習うローマ字。英語を習うときには「役に立たないどころか邪魔」なのだが、なぜ邪魔なのかがわかる本。後輩のカッキー君が教えてくれた大母音推移の勉強のために買ったんだけど、それ以外の歴史も書いてあっていい感じ。お勧め。
2006/03/20
■ ぐるぐる / 超人ロック伝説
tmtmさんとこで 超人ロック・ライザ第2話を見て、そこから「電脳かば」の管理人のブログへ。
さすが、超人ロックというべきか、なんともはや...
2006/03/19
■ ぐるぐる / 代金引換を悪用した詐欺まとめ@Wiki
代金引換を悪用した詐欺まとめ@Wiki。押し貸しが報道されたときに、この手口を思いついたのだが、 既に実用化されてたのか...とりあえず、この記事を印刷して家族に教える。
この手の知識が「まとめサイト」として簡単に手に入るようになったのは 実にいいことなのだが、そのまとめサイトへ到達できるかどうかが問題か。 デジタルデバイト?
オレオレ詐欺の類が長らく収束しなかったことを思えば、この詐欺も しぶとく続くんだろうなあ。
いま思えば、まとめサイトって、fjやusenetのFAQの再来だよなあ。
2006/03/16
■ 2ch / 鉄道模型を捨ててから、夫の様子がおかしい
鉄道模型を捨ててから、夫の様子がおかしい。旦那さんかわいそすぎ。
2006/03/10
■ Multi-Touch Interaction Research
WindchaseやiandethからYourTube:Multi-Touch Interaction Research。オフィシャルサイトはMulti-Touch Interaction Research。ひさしぶりに、凄すぎるモノを見てしまった。欲しいぞ。
こういうののプログラムって、どんな雰囲気なんだろうな。
2006/03/09
■ 測量商法
"測量商法"というものがあるらしい。頭いいなあ...
<****:#XXX> そんな測量に俺様がクマー
■ user.js / はてなわんわんワールド
はてなわんわんワールドに吹き出し表示切替機能を付けるGMスクリプト。firefox用だけど、Operaのuser.jsとしてもそのまま動いた。お勧め。
そういえば、わんわんワールド、Opera9 TP2 でもそこそこ使えるようになってる。
2006/03/08
■ 怪しいボランティア
3月4日に怪しい募金が来たという話を書いたのだが、マイミクの一人の家にもあやしいボランティアが来たらしい。こちらは「野の花会」を名乗っていたとのこと。
最近、訪問強化月間なのかしら。
■ はてぶ / この人なら知っています。沖縄の人だ
読んでください。
■ どうぶつの森
寝る前には門を開けましょう...
2006/03/07
■ 雑誌がたくさん...
いろんな雑誌を講読していると、読む順序がぐちゃぐちゃ。 連載が少ないからまだなんとか読める。
■ 雑誌 / 日経コミュニケーション 12.15
日経コミュニケーション12.15。特集は「エントリーVPN」。 各キャリアが出している安価なVPNの話。見落としがちな落とし穴の話が 参考になった。
■ 雑誌 / 日経コミュニケーション 2.15
日経コミュニケーション2.15。特集はダイナミックインターネットVPN。 網端のルータ側をもうちょっとかしこくして、メッシュ構成とかを 簡単に構築・変更できる仕掛け。面白い。 かなり大規模ユーザー向けだよなあ...
他には最近Web界で話題の「急成長GyaOで露呈したプロバイダのぜい弱性」。 いままでも何度も危機はあったけど、なんとかなってるんで、なんとかなる んじゃないかと、楽観。
■ 雑誌 / 日経エレクトロニクス12.19
日経エレクトロニクス12.19。特集は「ソフトウェアは硬い」。 まあ、ソフトウェアやってる人から見たらある意味当たり前の話。 とはいえ、他者からどう見られてるか、どう対応するかの参考になった。
■ 雑誌 / 日経エレクトロニクス1.2
日経エレクトロニクス1.2。特集は「研究開発 物理に還る」。 こういう記事が日経NEの醍醐味。
■ 雑誌 / パリティ 2006.02
パリティ2006年02月号(丸善株式会社)
「ファインマンレクチャーはいかにしてつくられたか」「高温超電導体の応用が始まった」が目を引く。
前者は、ファインマン物理学の元となった講義がどのようにして行われたかの回顧記事。興味深い。
■ 雑誌 / パリティ 2006.03
パリティ2006年03月号(丸善株式会社)
連載の「アリスの量子力学」が最終回。今回は量子情報。 量子計算とか量子暗号の話なんだけど、量子ビットを球で表すのは斬新。 すげーわかりやすい。この部分だけでも買う価値ある。
■ 雑誌 / 日経サイエンス 2006.04
日経サイエンス2006年4月号(日経サイエンス社)
特集は「子育てで賢くなる母の脳」。子供を育て上げる確率を高めるために 脳にさまざまな影響があるという話。言われてみればさもありなん。 母は強し。
「あなたのゲノム解読します」は、個人の遺伝子の解読コストが劇的に 下がった世界で何が起こるのかの推測。そういう推測が載る時代になったか。
■ 雑誌 / 紙の爆弾 2006.3
紙の爆弾 2006年3月号。まあいつもの内容。アルゼ関係記事多数。
■ 雑誌 / 國文學 2006.1
いまどきWebを持っていない、めずらしい出版社。 amazonでもfujisanでも見当たらない。 教えて!gooで、探してる人がいるぐらい...そもそも国文学じゃなくて國文學だし(以下、國という字はそもそも、と薀蓄をたれたくなるが我慢)。
特集は、「古事記・日本書紀比較」。これのために買った。 難解だけど、読めるところだけ読んでいく。写本の写真が載ってるのがいい。 岩波など代表的な書記の本の底本である卜部本が、比較的新しい体裁の 写本であるという記事は面白い。
こういうの読むと写本欲しくなるし、広告載ってるけど、買える金額じゃない... いや、買えないことはないか...
■ 雑誌 / 言語 2006.2
月刊言語2006年2月号(大修館書店)
特集は「聞くことが拓く世界」。巻頭の「認知科学のフロンティア」で「実在しない聴覚刺激を補完して音源を解釈する脳」という対談がいい。単行本にならないかな、これ。
■ しかし、雑誌
いったい、月に何冊読んでるんだ、俺。 昔(1980年代後半)は雑誌と本を合わせて、月に30冊ぐらいだったのに。 しかも電車通勤で読む時間はいくらでもあった時代 (読む金はなかったかもだ)。
疲れたので本の紹介はまた後日...
2006/03/06
■ ソフトバンク、ボーダフォン買収
そのうち、駅前でボーダフォンの携帯を配るという戦術に出そうな気が...
リンク:
2006/03/05
■ 飲みすぎ注意
1日中寝てる。
2006/03/04
■ 怪しい募金 / 国際救援友好協会
4年ほど前に、SHINZENを名乗る怪しい募金団体が来ていたのだが、またしても怪しい募金がやってきた。
最初は妻が相手をしていたが、らちがあかないので私が対応。 (話はさっぱり聞かなかったんで詳細わからんけど)ウガンダ難民救済が目的との こと。身分証明証のようなものを貼ったパンフレット(IRRFだったかな)を 見せて明るい声で話してくる。うさんくささがかなり減ってるし、 ねーちゃん結構美人。20代前半?
んでまあ、例によって「最近は怪しい団体も多いので、こちらで調べてから連絡します。連絡先を教えて」と言ったら素直に証明書を見せてくれた。
ジャンボの会
○○ ○○ (名前は伏せておきます。偽名かもしらんけど)
国際救援友好協会
住所と電話番号もメモしたけど、伏せておきます。 んで、さっそくgoogle様に問い合わせしたら... 「ジャンボの会」は同名の団体多数。スワヒリ語の点訳をしている団体がヒットするけど、これではなさげ。
「国際救援友好協会」(IRRF)がどんぴしゃ。やっぱり「統一教会」でした... 「ジャンボの会」は偽装ですね、きっと。
あーあ。結構美人だったのにもったいないなあ... 以下参考リンク。
- カルト被害を考える会 - 統一協会が戸別訪問によく使う「ボランティア団体」の名前
- http://ja.wikipedia.org/wiki/国際救援友好協会
- つれづれメモ - 2002-05-05 とても悲しいこと
- Text - 寄付日記
- チャンネル桜掲示板
■ OIA勉強会
今日は学生さんの発表。突っ込みすぎをたしなめられる。
宴会。その後、ヨタ話へ...
2006/03/03
■ 40前後の元マイコン少年のためのREST/Web2.0解説
わんわんしていて気がついたことを書きます。
RESTってのはGETとかPUTとかの規約だって思ってて、良くわからなかったんだけど、 実はC言語で言うところの関数呼び出し時の規則なんだなって気がつきました。
MS-DOSのシステムコールは、 int 21hでahにファンクション番号を入れて、 ファンクションごとに変わる指定のレジスタに情報を格納して呼び出し、 ファンクションごとに決まっているレジスタに値が返ってきました。
メモリがなくて1命令でも減らしたい時代は、どのレジスタで受けてどのレジスタで返すかは、重要な問題なんで、まあ、これが普通なわけです。
C言語が導入されると、関数呼び出し規則が定まって、レジスタをどの順に使って 戻り値はどのレジスタで返すとか自然に決まっちゃったわけです。 その結果としていろんなライブラリが作成できて、いろんなことができるようになりました。
RESTってのは、ここで言うところの「関数呼び出し規則」なんじゃないかな。 単なる関数呼び出し規則に名前を付けるから混乱するわけで、 本来は「次なる高級言語」というか「メタ言語」のための「サーバー間RPCのための呼び出し規約」がRESTだと。
すると、googleとかamazonがAPIを公開しているのは、(まさしくAPIの公開なわけで)、 次世代の printf を誰が提供するかという勝負をしているようなもんじゃないかと。 次期UNIXのlibcやstdio.hを作ってるんだと。
しかも、Cのライブラリと違って配布する必要がないんだよな。
googleやはてなは頭いいなーと思った、夜でした。
おわり
追記: google は 21世紀のベル研なのかも(笑)
2006/03/02
■ はてなワンワンワールド
説明ははてなワンワンワールド、遊ぶ場所ははてなわんわんワールド。要はてなのアカウント(無料)。
google mapsを使ったチャット、と言ってしまえば それだけ何だけど、 妙な面白さがある。先週末にリリースされ昨日あたりからブレークしつつある感じ。
とりあえず、県内某所にいます。わんわん。
Tips: Opera9 TP2 では、ともだちリストがうまく動かなかった。firefox 1.5 はOK。
また君か-はてなワンワンワールド雑感の説明が分かりやすいかも。
追記: いつのまにか、駅に説明の吹き出しが立ってる。進化してるなあ。