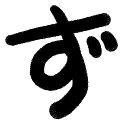2007/02/26
■ 本 / バビロニア・ウェーブ
バビロニア・ウェーブ、堀晃 著、創元SF文庫。
日本のハードSFといえば堀晃だと私は思っている。 その堀晃の唯一の長編の初めての文庫版。 fukkan.comのおかげで復刊された。
私が堀晃を知ったのは文庫で梅田地下オデッセイが出たあたりで1981年ごろ。その後のトリニティシリーズや情報サイボーグシリーズなど 真っ向からエントロピーとかエネルギーの収支とかを扱ったSFを書いている。 短編ばかりの寡作な作家で、wikipedia:堀晃を見ても作品が本当に少ない...そのために作品が絶版になるのも多く、入手は困難。
で、本書も期待にたがわず面白い。SF好きなら買うべきです。 若干内容は古いですが(原作は1988年)、十分楽しめます。
そうそう、梅田地下オデッセイは、作者のWebページで 読むことができます。でもまあ、まえがきにもあるけど、解説の図解が重要なんで 本を入手されることをお薦めします (うは、文庫の癖にアマゾンマーケットプレイスで2800円とか4400円とかついてる...)。
■ 本 / GADV仮説—生命起源を問い直す
GADV仮説—生命起源を問い直す池原健二 著、京都大学学術出版会。
生命の起源の話になると、どうしてもDNAとタンパク質の「鶏と卵」問題になる。 DNAがないと遺伝情報の蓄積ができないし、タンパク質がないとDNAの複製や代謝が できない。最近では、RNA単体でも遺伝情報の蓄積ができることと、 触媒作用ができることで、最初にRNAありきの「RNAワールド仮説」が 有力視されている。RNA干渉なんてのも見つかったし。
本書は「いやいや最初はタンパク質なんだよ」という説。 最初はGADV - グリシン・アラニン・アスパラギン酸・バリン の4つのアミノ酸から できるタンパク質で代謝が成立し、そこから遺伝子暗号、遺伝子が加わり 共進化して生命につながったとする。
たしかに、一番最初はRNAよりもタンパク質ができやすかっただろうし無理がないが、 そこからどうやってRNA/DNAにつなげるかがちょっと難しい。 説は整理されて読みやすいし、RNAワールド仮説の本と一緒に読むといいと思う。
2007/02/24
■ Nintendo DS / レイトン教授と不思議な町
レイトン教授と不思議な町、レベルファイブ 、Nintendo DS
アドベンチャーゲームになるんだろうか。頭の体操的な謎解きで進んでいくゲーム。 テンポ良く話は進むし、所々に入っている動画も良い。 オタっぽくない、ジブリっぽい感じの動画と音楽が雰囲気を出している。
謎とメダル探しに画面の隅々を調べるのは、「これなんて 惑星メフィウス?」状態だけど、タッチペンのおかげで あまり苦にはならない。
ストーリーも良く、終わりは感動的だった。 佳作だと思う。お勧めします。
■ Nintendo Wii / ラビッツ・パーティー
ラビッツ・パーティー、ユービーアイ ソフト 、Nintendo Wii
YouTubeでCMを見て気になっていたソフト。 世界樹の迷宮がそろそろ終盤なので次に遊ぶゲームを物色して購入。
変に可愛い?ウサギが出てくるミニゲーム集。 はじめてのWiiの次ぐらいにやるといいんじゃないかなあ。音楽はディスコミュージックだし、やってて懐かしいというかなんというか。 Wii肉痛になるのは必至なので、少しずつやるのが吉かと。
複数人で遊ぶときはヌンチャクコントローラーが人数分必要なので要注意。
2007/02/23
■ Nintendo DS / 充電USBケーブル
ircで話が出たのでメモ。 4機種対応 ACアダプタ /。AC/USBから充電可能で、DS Lite, DS, GB SP, PSP の充電が可能。 ACアダプタにはUSBポートがあるので、他のUSB対応機器の充電もできる。
■ 雑誌 / 月刊少年ジャンプ休刊
2007/02/23-12:57 月刊少年ジャンプが休刊(時事通信)。 これは困った。Claymoreはどうなるんだろう。いいところなのに。 コミックスはCLAYMORE 11まで出てる。
2007/02/19
■ 本 / 日本はなぜ敗れるのか—敗因21ヵ条
日本はなぜ敗れるのか—敗因21ヵ条、山本七平 著、角川書店。
山本七平 の著作には、日本人とユダヤ人など有名な本も多い。だが、なんとなく食わず嫌いでいままで手に取ったことは無かった。 出版時期が1970-1975年あたりで、まだ小学生の私が手に取るには早すぎたのかも しれない。
さて、本書は、太平洋戦争当時のある個人の記録(虜人日記)を元に、戦争の敗因について克明に書いた本である。そのような本としては、失敗の本質—日本軍の組織論的研究が良書だし私も薦めていたのだが、本書に比べればまだ「キレイゴト」であったと 痛感させられる。特に第二章「バシー海峡」。ここだけでも読む価値がある。
本書で述べられている教訓は、まったく今の日本に活かされていないのも残念 (今の若い人は良くはなっているような気もするけど)。 本書の帯が「トヨタの奥田碩会長お薦め」になっているのが、なんとも逆説的。
ここ数年で読んだ本でもっとも良い本だと思う。一読を強くお薦めします。
追記1: ちなみに、この本の南京虐殺のあたりは同意できない部分あり。 ただし、そこを除いてもいい本だと思う気持ちには変わりはない。お勧めである。
追記2: このエントリを読んで買ってくれた方が何人かいらっしゃいます。感謝。
- 逃げ道さん(mixi)
- 日本はなぜ敗れるのか—敗因21ヵ条(山本 七平)(kojのとりあえず日記)
■ 本 / 個体発生は進化をくりかえすのか
個体発生は進化をくりかえすのか、倉谷滋 著、岩波書店。
岩波書店の科学入門である岩波科学ライブラリー の一冊。それほど分厚くもなく手軽に読める本。
書名の通り生物の個体発生と系統発生についての本である。 7割ほどは従来の学説のおさらいで、最後に筆者の考えが書かれている (amazonの書評を読むと筆者の考えがないと誤解している人が多いようだが、そうではないと思う)。
ネタばれになるのでここでは詳細は書かないが、 最後に展開されている筆者の説は妥当であると思うし、検証可能であるように思う。 また、この考え方は他のことにも応用できそう。OSの進化とか。 筆者の類書も読んでみようと思う。進化に興味がある人は読んで損はないと思います。
本書も含めて岩波科学ライブラリー は結構いい感じだと思った。昔のブルーバックス みたいに集めてみたくなる。とはいえ、全巻そろえるには値段はやや高め(1200円)だが、 物価水準を考えれば妥当かなあ。
■ 本 / オイラー、リーマン、ラマヌジャン—時空を超えた数学者の接点
オイラー、リーマン、ラマヌジャン—時空を超えた数学者の接点、黒川信重 著、岩波書店。
素数論とかゼータ関数の本。筆者の黒川さんは数学セミナーなどで時々 ゼータ関数の話を書いていて、でもよくわからないので、入門書なら、と買ってみた。
で、やっぱりわからんなあ、これ。 最初の素因数分解の一意性あたりはいいんだけど、謎のくりこみ計算あたりで 話がわからなくなる。そのへんをわかりやすく書いた本はないものか。
2007/02/18
■ Nintendo DS / 世界樹の迷宮 / 20F
相変わらず、世界樹の迷宮 をやっている。ようやくB20F。いきなり難しくなった。どうしたらいいんだろう、ここから。
■ Nintendo DS / DS時雨殿 その5
タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿、ついに娘に抜かれた。102枚。凄い。 私が世界樹にはまってるせいもあるけど。
2007/02/17
■ 本屋
秋葉原の書泉ブックタワーが、どうも私の好みから外れつつある。 いまのお気に入りは丸の内のoazo内の丸善。
2007/02/16
■ 神田まつや
吉浜さんの案内で、まつやという蕎麦屋へ。 いやー、いい店だわここ。意外な東京というかなんというか。
しかし、東京ってのは凄いところだね。いろいろ勉強になりました。
2007/02/14
■ Nintendo DS / 世界樹の迷宮 / 12F
世界樹の迷宮 をデザインした新納さんがアトラスを退社したそうだ。ガーン。 Nintendo Insideのインタビューを読んでから、次回作に期待していたのに...
2007/02/12
■ Nintendo DS / 世界樹の迷宮 / 10F
世界樹の迷宮、ようやく10Fにたどりつく。まだ10Fのボスは倒していない。レベル32でやや遅めの展開。 しかし面白い。時間無くなる。
■ 本 / 新・民族の世界地図
新・民族の世界地図、21世紀研究会編集、文春新書。
言語・宗教・移動・対立・紛争など、さまざまな観点から民族についての 情報・知識を書いた本。筆者のグループは非常に博識で、表面だけではなく 結構深いところまで記述されている。おかげで新書にしてはちょっと厚め(300頁) だが、読む価値はある。
しかし、この本で民族対立の歴史を読んでるとアングロサクソンが嫌いになるね。 植民地時代の分割統治により、それまでは同居していた民族を反目させて 統治を楽にしていた政策が、植民地時代の終わりと共に紛争を招いている ということがよくわかる。
国際情勢や民族問題に興味がある人には強くお勧め。 一般常識として読むのもいいと思う。
■ 本 / インテリジェンス 武器なき戦争
インテリジェンス 武器なき戦争、手嶋龍一 著、佐藤優 著、幻冬舎。
著者の一人の佐藤優は元外務省勤務のロシア通。 ムネオ疑惑で起訴されたので知ってる人も多いと思う。
本書はインテリジェンス(諜報活動とか情報戦争とかにあたるか)について、 対談形式で語っている本。これ、そのまま参考にしちゃっていいんですかねえ。 問題が問題なだけに微妙なところは避けているし、悩ましい。 時間が解決するんだろうな。次回作に期待しよう。
■ 本 / 物語 ウクライナの歴史—ヨーロッパ最後の大国
物語 ウクライナの歴史—ヨーロッパ最後の大国、黒川祐次 著、中公新書。
中公新書の歴史物語シリーズ。長らくソ連の一部としてしか見られてこなかった ウクライナ。 私がウクライナを知ったのはチェルノブイリ原子力発電所の事故のころで、 もう20年以上前になる。大学を卒業して入社した直後(1986年4月26日)に 事故が起こった。とは言え、それからも私の意識としてはソ連の一部であり、 1991年の独立後もそれは変わらなかった。
本書では、そのようなソ連の一部であるウクライナ観ではなく、 むしろロシアに先んじた大国であるウクライナの歴史を説く。 詳細は本書に譲るが、一読後はウクライナとロシアに対する見方が変わるだろう。
先日読んだバルト三国の歴史で書かれているリトアニアとは地域が隣接していることもあり、 双方の本での記述の違いを読むと、いっそう楽しめる。 ヨーロッパの歴史というのは、日本の歴史とは全然違うと痛感させられる。
また、ヨーロッパ東部の歴史を読んでいるとモンゴルの重みが伝わってくる。 なんというか、ロシアってモンゴルの後裔なんじゃないかと思ったり。
■ 本 / やりなおしの将棋
去年読んだ 最強の駒落ちの著者による大人向けの将棋入門本。棒銀・矢倉・四間飛車までの基本定石も書かれている。
去年の12月の日記でも書いたけど、最強の駒落ちにつられて買ったいつでもどこでも できる将棋 AI将棋DSに全然勝てないので少しは昔に戻って勉強しようと思って買いました。 おかげで5級ぐらいで足踏みしていたのが4級までは進めるようになった。 あとはポカミスを無くせばもうちょっと先にいけるかなあ...
■ 本 / コンピュータ囲碁の入門
コンピュータ囲碁の入門、清愼一著、佐々木宣介著、山下宏著、コンピュータ囲碁フォーラム編集、 共立出版。
コンピュータ囲碁プログラムの作り方の本。 実際にC言語で書かれたソースがCD-ROMで添付されてくる。 コンピュータ将棋の本は多いのだが、囲碁はゲームそのものが難しいこともあって 本が少ない。興味がある人にはお勧め。
2007/02/10
■ Nintendo DS / 世界樹の迷宮
世界樹の迷宮、アトラス、Nintendo DS。
昨日、おもろまちのTSUTAYAで入手。残り1個。入荷数が少ないのかな。
前評判を聞いていたので期待して始めたけど、いやーこれ、面白いわ。 公式サイトで 作者の新納さんが語ってるように、3DダンジョンRPGの可能性を見せてくれるようなゲームだと思う。
Wizardry I のような、ハードな展開。 Wizardry I や Might & Magic I のようなマッピングの楽しみ。 Dragon Quest I (II,IIIあたりまで?)の戦闘の楽しさ、 Might & Magic I のような謎解き(クエスト) 基本的なシステムは Wizardry I (特に武器屋)。 いいとこどりというか、いままでの名作の面白さのポイントをよく研究していると思う。
ということで、一日つぶして3Fぐらいまで。 マップに残る謎が興味をそそる。
Wizardry I の Apple 版あたりに似せたのか、複数セーブができない。 複数人プレイもできない。 家族でやるには人数分必要だ...でも、こんなのやらせたら人生無駄遣いだな。
2007/02/09
■ Opera / 起動・操作が重たい
Linux版のOpera使ってて、時々動作が非常に遅くなる現象発生。 再起動しても再起動そのものにも異常に時間がかかるし、治らない。 以下、調べてわかったこと。
- OperaのRSSリーダーはメールと同じモジュールで作られている。
- メールを溜め込みすぎると動作が遅くなる現象が報告されている(→Operaのメーラーで特定のメールを保護して残りを全部消す方法)
- RSSフィードで得られた項目は ~/.opera/mail/ の下に1項目1ファイルとして保存されている
- Opera起動時には、それらのファイルを全部?読むようだ。lsof してみたら、莫大な数のファイルが開かれていた。
結局、RSS Feed から要らない過去の項目を消すことで元の速度に戻った。 Operaってもしかして設計が富豪スギ?
2007/02/08
■ 暖冬 / 過去の天気
なんかの折に「今年は暖かいよね」という話になったので、 過去の天気を見てみる。今年のデータだけ見ると暖かい感じがするけど、過去に遡ると 近年はこれぐらいの暖かさが普通のようだ。 前世紀のデータ見れるところが探せなかったのだけど、どっかにあるかなあ。 前世紀はもっと寒かったような気がするので。
■ amazon / amazonアフィリエイト
今年から管理単位が四半期から1か月になっているのに、 管理画面が従来のままというおおらかさだったamazonだが、 今日から計算も1か月単位になっている。 泥縄な感じだが、そんなもんか。
と、思ったら、「今月」を選択しても「1月1日〜2月7日」までになるな。 なんじゃこれ。
2007/02/04
■ Nintendo DS / DS時雨殿 その4
相変わらず、タッチで楽しむ百人一首 DS時雨殿をやっている。150秒以内に何枚取れるかを競う「早取り」で75枚。 2秒に1枚だ。2ch見ると100枚以上取れる人もいるらしい。修行せねば。
2007/02/03
■ OIA / OIA勉強会
今回は琉大の学生さんの発表。 男の子は作る方に目がいっちゃって、暴走するんだよな、例年。
2007/02/01
■ amazon / amazonポイント開始
「Amazon ポイント™ 開始!」というアナウンスがありました。ざっとみた感じだと、書籍やCDで1%、エレクトロニクス関連で5%のポイントが付くようだ。
日経MJが2006年8月に出した書店の総売上高経常利益率ランキングが日本著者販促センターのサイトに掲載されているけど、 これを見ると中古を扱っていない普通の書店では、利益率はせいぜい3%で、1%以下や赤字のところも多い。
amazonに書籍のポイントを1%も付けられたら、書店は大変だと思う。 対抗しようにもそもそも利益率が1%を切っていたら厳しいし、 客注もamazonにスピードで負けるし、 よっぽど地域の客を掴んでないとつらそうだ。
で、このポイント、2月1日午前8時15分以降の買物で有効らしい。 たまってたギフト券を夜中の2時頃使った私は負け組...